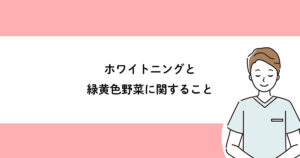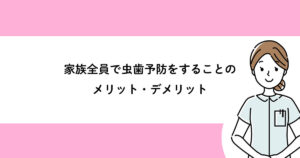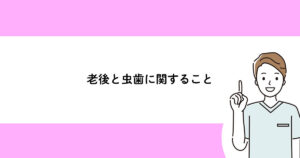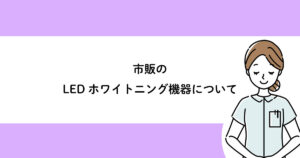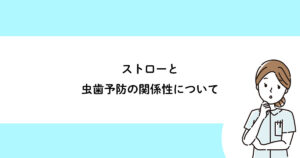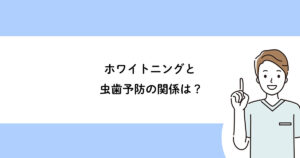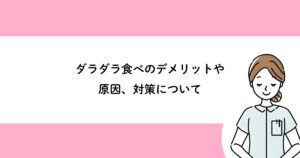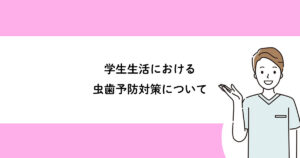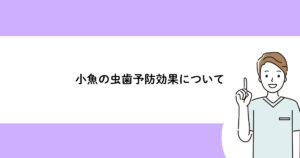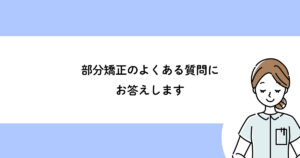親御さんにおける重要な役割の一つに、子どもの虫歯予防が挙げられます。
健康な身体に育て上げるためには、虫歯を発症させないことも考えなければいけません。
またこのとき、虫歯予防の一環として子どもにキシリトール配合食品を与える方がいます。
今回はこちらのメリットや注意点などについて解説します。
キシリトール配合食品の概要
キシリトール配合食品は、名前の通り天然の甘味料であるキシリトールを配合した食品です。
具体的にはガムやタブレットなどが挙げられます。
子ども用キシリトールガムには、まだ咀嚼力のない子どもでも食べやすいように、やわらかくつくられているものがあります。
またタブレットやキャンディは、口の中でゆっくり溶かすことで効果的にキシリトールを摂取できます。
ちなみに食品以外でいうと、キシリトール配合の歯磨きジェルや歯磨きシートは、歯が生え始めた赤ちゃんにも使用できます。
子どもにキシリトール配合食品を与えるメリット
子どもにキシリトール配合食品を与えるメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
・虫歯菌の活動を弱める
・プラークを剥がれやすくする
・唾液の分泌を促す
・歯の再石灰化を促す
・安全性が高い
各項目について詳しく説明します。
虫歯菌の活動を弱める
キシリトールは、虫歯の原因となるミュータンス菌が分解できないため、酸が作られません。
これにより、菌の活動を弱めることができます。
プラークを剥がれやすくする
キシリトールの作用により、プラークのネバネバとした塊(菌体外多糖)を溶けやすくします。
そのため、プラークが歯に付着しにくく、ブラッシングで除去しやすくなります。
唾液の分泌を促す
キシリトール入りのガムなどを噛むことで唾液の分泌が促されます。
唾液には歯の再石灰化を促したり、口内を中性に保ったりする作用があります。
歯の再石灰化を促す
キシリトールは唾液の働きとあわせて、溶けかけた歯の表面のエナメル質を修復する再石灰化を促し、歯を強くする効果も期待できます。
安全性が高い
キシリトールは天然の甘味料で、食品添加物として厚生労働省に認可されており、安全性が高いとされています。
そのため、親御さんは子どもに対しても安心して使用できます。
子どもにキシリトール配合食品を与える際の注意点
キシリトール配合食品は子どもの虫歯予防を行うにあたって最適ですが、摂取させる際は以下の点に注意してください。
・多量摂取による下痢
・虫歯の原因となる成分が含まれることがある
・効果的な摂取方法がある
・過信しない
各項目について詳しく説明します。
多量摂取による下痢
キシリトールは消化吸収されにくいため、一度に大量に摂取するとお腹がゆるくなることがあります。
そのため、特に胃腸が弱い子どもは注意が必要です。
虫歯の原因となる成分が含まれることがある
市販のキシリトール配合食品には、キシリトール以外の甘味料(砂糖や水あめなど)や、歯を溶かす酸(クエン酸など)が含まれているものがあります。
虫歯予防を目的とする場合は、キシリトール100%配合で、なおかつ砂糖や果汁を含まない製品を選ぶことが大切です。
またこのようなキシリトール配合食品は、歯科クリニックで販売されていることがあります。
効果的な摂取方法がある
虫歯予防の効果を得るためには、正しいタイミングと量を守って与える必要があります。
具体的には、食後や間食の後に、1日数回に分けて摂取すると効果的です。
過信しない
キシリトールは虫歯予防をサポートする食品であり、歯磨きやフッ素塗布といった基本的なケアを代替するものではありません。
親御さんは、キシリトールだけで虫歯が完全に防げるわけではないことを理解しておく必要があります。
その他の注意点
子どもにキシリトール配合食品を与える場合は、飲み込むリスクを考慮して、奥歯が生えそろう1歳半ごろからタブレット製品などを与え始めるのが目安とされています。
このとき、大きいタブレットは、小さく砕くなどの工夫が必要です。
また一部の研究で、多量のキシリトール摂取と心臓発作や脳卒中のリスク上昇との関連性が指摘されています。
ただし、この研究は大人を対象としたものであり、さらに多くの研究が必要です。
子どもが通常量摂取する上でのリスクについて、現時点では明確な結論は出ていません。
ちなみに、自宅でキシリトール配合食品を保管する場合は、犬などのペットの手の届かないところに置くことが望ましいです。
キシリトールは人間にとっては安全ですが、犬にとっては非常に危険で、ごく少量の摂取でも中毒を起こす可能性があります。
まとめ
子ども用のキシリトール配合食品は基本的に安全ですし、虫歯を予防するためのさまざまな効果を発揮します。
そのため、1歳半くらいの子どもを持つ親御さんは、少しずつ採り入れていくことをおすすめします。
もちろん注意しなければいけないこともありますが、摂取させる方法やタイミング、製品の選び方などを間違えなければ、大きなトラブルは回避できます。