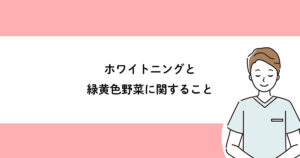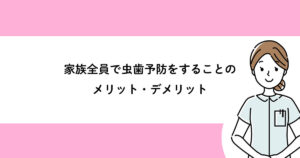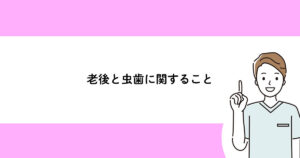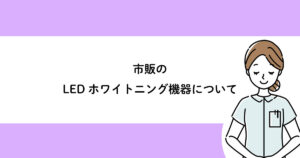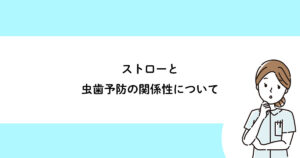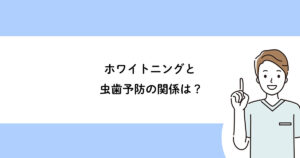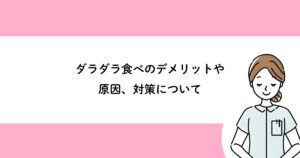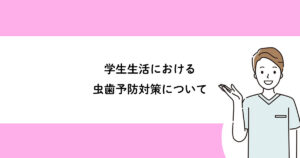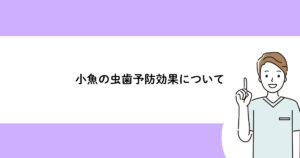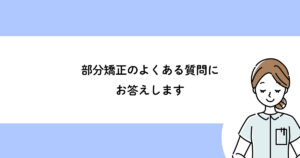歯周病は、単体で発症するだけでも極めて厄介な疾患です。
歯茎が炎症を起こしたり、出血したりすることで日常生活に支障をきたす上に、口周りの審美性も低下します。
また歯周病と併発することでより厄介になる疾患として、咬合性外傷というものが挙げられます。
今回は、歯周病と咬合性外傷の併発に関することを解説します。
咬合性外傷の概要
咬合性外傷は、過度な噛む力が歯や歯茎などの歯周組織に加わり、その組織に損傷を与えるというものです。
主に以下の2種類が存在します。
・一次性咬合性外傷
・二次性咬合性外傷
一次性咬合性外傷は、健康な歯周組織を持つ歯に、通常よりも強い咬合力が加わることで発症します。
こちらは歯ぎしりや食いしばりといった、本来の咀嚼以外の強い噛み癖が原因になるケースが多いです。
ここでいう咀嚼以外の強い噛み癖は、パラファンクションとも呼ばれます。
また一次性咬合性外傷は、歯周病を直接発症させるわけではありませんが、歯に負担をかけることで歯の動揺などを引き起こすことがあります。
そして二次性咬合性外傷は、すでに歯周病によって歯を支える歯槽骨が失われ、歯周組織が弱っている間に通常程度の咬合力が加わることで発症します。
歯周病によって歯の支えが減っているため、わずかな力でも負担が大きくなり、歯周病の進行をさらに加速させます。
歯周病と咬合性外傷を併発することのデメリット4選
歯周病と咬合性外傷を併発してしまうことにより、以下のようなデメリットが生まれます。
・歯周病の悪化
・歯の動揺
・噛むときの痛み
・歯の移動
各デメリットについて詳しく説明します。
歯周病の悪化
先ほども少し触れましたが、咬合性外傷による強い力は、歯周病による炎症をさらに悪化させ、歯槽骨の吸収を速めてしまいます。
歯周病はただでさえ発症や進行に気付きにくい疾患ですが、このように進行が速まることにより、気付いたときには重度にまで達していることも珍しくありません。
歯の動揺
咬合性外傷によって歯に過剰な力がかかると、歯がグラグラと揺れるようになります。
すでに歯周病を発症している方は、当然歯の動揺によって脱落のリスクが高まります。
また歯周病を発症していない方であっても、歯がグラグラと揺れるようになるのは大きなデメリットです。
噛むときの痛み
咬合性外傷を発症すると、歯根膜が傷つくことがあります。
歯根膜は、歯の根元にある歯と骨をつなぐクッションのような組織であり、こちらが傷つくとものを噛んだときに痛みが出やすくなります。
特に歯周病と併発している場合、ただでさえ歯茎の炎症によって痛みが出ていることがあるため、咬合性外傷によってその痛みはさらに強まります。
歯の移動
咬合性外傷は、歯ぎしりや食いしばりのように、歯周組織に対して強い力が継続的にかかり続ける疾患です。
そのため、発症することで歯がずれたり、傾いたりすることがあります。
また歯周病を発症している方は、歯茎がやわらかく歯が動きやすい状態になっているため、このような影響を特に受けやすいです。
歯周病と咬合性外傷の治療におけるポイント
歯周病と咬合性外傷を併発している場合、以下のポイントを押さえた治療を受けなければいけません。
・炎症の治療
・噛み合わせの調整
・歯の固定
まずは、歯周病の症状を改善させるためのアプローチが必要です。
具体的には、歯周病の原因となるプラークや歯石を除去し、歯周組織の炎症を抑えます。
このとき歯科クリニックで行われるのはスケーリングやルートプレーニングと呼ばれるもので、歯周病治療における基本中の基本とされています。
もし歯周基本治療だけではない対応できないのであれば、歯周外科治療や歯周組織再生療法なども適用されます。
歯周外科治療は、歯周基本治療では届かない深い歯周ポケットの歯石を除去するため、歯茎を切開する手術です。
歯周組織再生療法については、失われた歯茎や骨といった歯周組織について、特殊な材料で再生させる治療です。
中程度の歯周病が対象になるケースが多いですが、すべての症例に適用できるわけではありません。
また咬合性外傷も併発している場合、歯周病の治療後に噛み合わせの調整を行わなければいけません。
こちらは歯の被せ物の形を調整したり、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合はマウスピース(ナイトガード)を装着したりして、歯にかかる過度な力を軽減させます。
あまりにも歯の動揺がひどい場合は、隣の歯と連結して固定することで安定を図ることもあります。
ちなみに、歯周病が末期にまで進行している場合、残念ながら抜歯をしなければいけないこともあります。
まとめ
歯周病は発症率が高いにもかかわらず、発症しても気づきにくい疾患です。
そのため、日頃からブラッシングなどのセルフケアを徹底し、早期発見のために定期的に歯科クリニックに通うことも大切です。
また咬合性外傷についても、歯ぎしりや食いしばりがあったり、それほど強い力で噛んでいなかったりする場合、すぐに発症していることに気付くのは困難です。